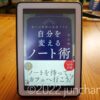「遅読」のすすめ。あえて遅く読むことで、得られるものは多いと教えてくれる本
齋藤孝さんの『「遅読」のすすめ』を読んだ。
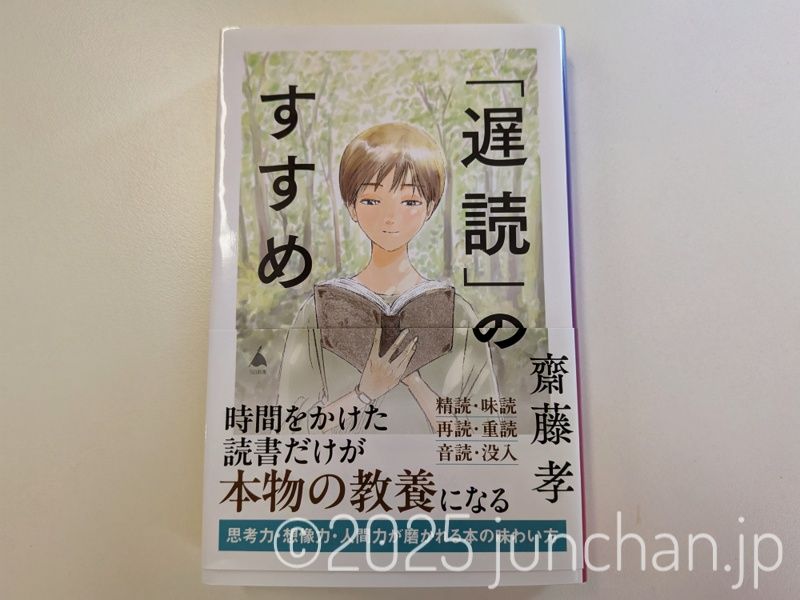
書店に行けば「本を早く読む」ことをテーマにした本の方が多数派な印象だが、本書は逆に、あえて「本を遅く読む」ことをテーマにした本だ。
本書を書店で見つけて、遅く読む方を扱っているなんて返って新鮮に思え、なんとなく気になったので手にしてみたのだった。
「遅読」のすすめ
先に書いたとおり、書店では「本を早く読む」ことをテーマにした本が多い中、本書は「本を遅く読む」ことをテーマにしている。
本を早く読むことを主眼にすると、「本というのは情報収集のために読むもの」という捉え方が前提になるだろうか。だから素早く、大量に情報を仕入れることを良しとするのが速読の訴えるメリットである。
本書はそういった姿勢に対するアンチテーゼとして書かれているような感じがする。
コスパ・タイパの時代だからこそ「味わって読む」理由
と裏表紙に書かれているとおり、本を味わって読むことで得られることを本書では説いている。
とはいえ、速読を否定するというよりは、本の種類や、本を読む目的によって、本を読む速度を変えてみるのもいいんじゃないか、くらいのスタンスだ。
例えば、本書のような新書であれば、まずはさっと全体を読んでしまって、その中で気になったところを改めて何度も読み直す、といった読み方が紹介されている。
そんな感じで、早く読むことだけがいいわけじゃなくて、遅く読むことにも価値はあるわけで。というか、どんな本でも、終始一定の速度で読めるわけでもなく、自然と遅くなることだってあるだろう。それを良しとするのだ。
読むためのスピードを決めるのは、読む側ではなく、本の方
といった記載もあって、まさにそうだよなと思う。
新書やビジネス書を読むのと、大学のテキストを読むのでは、スピードが変わって当たり前だろう、という話だ。
本当に情報収集のためだけに読むなら早く読むのもいいのだろうが、中にはじっくり考えて、あるいは、味わって読んだ方がいいものだってあるだろう。
昨今の、次々と生まれてくる、ほとんど考えないで読み飛ばしていけるような本ばかりを消費するのではなくて。
本を読むこと自体を楽しむというか。その時間を娯楽とするというか。
そう考えてみると、本を早く読むとか、遅く読むとかいうのはどうでもいいことな気がしてくる。ただ、その時間に浸るのだ。これはとても贅沢な時間といってもいいだろう。
最近、私は読書ノートを書いてみたり、ゲーム日記を書いてみたりしているが、こういった行為は、その体験をもっと味わうためにやっているのだろう、と本書を読んでいて納得してしまった。
そうやって、時間や手間暇をかけることで、ただなんとなく日々を消化していくんじゃなくて、体験したことを追体験して、じっくり味わうことこそ、人生に彩りをもたらすんじゃないかと思う。
こうして本書のことを振り返って、自分の体験に引きつけて書き出していく行為も、本書を味わうことであり、遅読の醍醐味のひとつなのかもしれない。
これまでは、どちらかというと本はどんどん読んでいくものだと思っていた気がする。本書によって、そのことに気づいた気がする。
むしろ、あえて遅く読むのもいいじゃないか、と。読んでいって、躓いて、本を閉じて、「これってどういうことだろう?」と考える時間も、読書の楽しみ方なんじゃないかな。
人は考えると疲れるから、できれば考えたくないものなんだけど、その欲求を優先するとほとんど読み飛ばしていけるような本ばかりになってしまう。そうして消費した時間が後から役に立つかというと、どうだろう?
そうではなくて、あえて考えるために本を読み、粘り強く考える時間を取ることは、これからの時代を生き延びるためにも必要な時間だと思う。
なお、本書の中では、遅読に適した本がいくつも紹介されている。古典的な本も多く、国語や歴史の教科書で学ぶような著者が書いた本もたくさん出てくる。それらの紹介文を読むだけでも時間がかかった。まさに考えさせられたのだ。
タイパとかコスパとかいう話でいうと、これらの本はかえってタイパもコスパもいいんじゃないかと思えた。だって、1冊読むのに時間がかかるし、何度でも読み返せる。その時間は貴重な体験になる。時間を置いて読むことでまた新しいことを考えるだろうし、時間を置くことでその世界観に浸っていくこともあるだろう。
本書は、本を読む速度や、本を読む目的、理由について、改めて考えさせられる本だった。