IO DATAのNAS「HDL1-LE02」(LAN DISK)導入から1ヶ月のレビュー。手軽に導入できるのは利点
IO DATAのNASブランドであるLAN DISK「HDL1-LE02」を導入して、1ヶ月が経った。
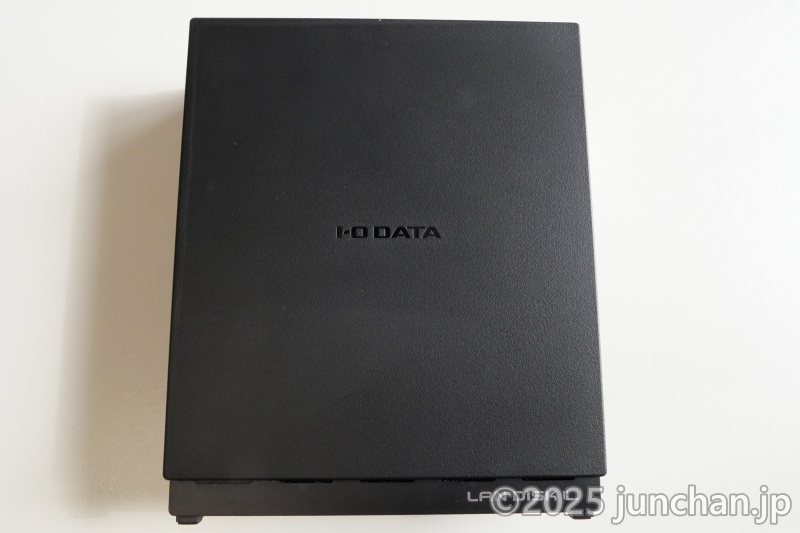
写真や動画ファイルのバックアップサーバーとして導入したのだが、実際1ヶ月使ってみてどうだったかをレビューしてみるとしよう。
写真、動画ファイルのバックアップ
LAN DISKの各種設定は、本機のWeb画面から確認、変更することができる。
バックアップ機能もここからポチポチと設定した。

設定自体は簡単なもので、サラッとできた。
そこからはバックアップも順調にできているようで、特に設定を変えたりすることはなかった。
バックアップ対象は400GB近いのかな?
初回は流石に時間がかかったが、差分バックアップで5世代まで管理するよう設定しているので、2回目以降は時間短縮されている。
とはいえ、1回あたりのバックアップは25~30分ほどかかっているようだ。バックアップ元に1ファイルの更新すらなくても、毎回そのくらい時間がかかっている。
これは、世代管理している都合で、差分があったファイルはコピーするし、差分がないファイルもLAN DISK内でハードリンクを設定しているから、結局、ファイル全量に何かしらの処理をしているためだろう。
時間が妙にかかっている気がするけど、これで毎日安定的にバックアップ処理が終わっているから、世代管理するならそのくらいかかるものなんだろうと思っている。
ファイルサーバーとして利用する
2TBもあるから、写真や動画のバックアップだけで使うのももったいないので、NASらしくオンラインストレージとしても使っている。
アクティブに読み書きするようなファイルではなく、昔から保管し続けているファイルの保管庫として使っている感じだ。
過去のセミナーの資料とか、仕事の文書とか、残しておくことにしているものを置いている。
こういうファイルは保管することは決めているんだけど、じゃあどこに置いておくのがいいかな?というのはちょいちょい迷いながら、置き場所が変遷してきたものだ。そういうものを置くのもいいだろう。
そのうち、この保管庫自体もバックアップしてやるのがいいのだろうな。
LAN DISKにはUSB端子があり、外付けドライブを拡張することができるようになっている。先のバックアップ機能を使って、NAS→外付けドライブというバックアップの設定ができるのだ。
NASそのものもバックアップしてやるとより冗長性が高まっていいだろう。
ただ、LAN DISKで使える外付けドライブには制約があって、何でも使えるわけではない。バスパワーモードのものは使えないし、動作確認しているのはIO DATAの一部のドライブだけだったりする。
そんなゴツい外付けドライブを買うくらいなら、もう1台LAN DISK買ってもよくね?と思わないでもない。値段もそう変わらんし。
ランディスク遠隔管理サービス「NarSuS」で不具合検出
LAN DISK導入時に、IO DATAが提供しているランディスク遠隔管理サービス「NarSuS」に登録した。
このサービスに登録しておけば、LAN DISKが異常時に通知をしてくれるというのだ。
仕組みとしては、LAN DISKが定期的にNarSuSにデータを送信し、NarSuS側でデータを確認して、異常があれば登録したメールアドレスに通知してくれる、というものだ。データが届かないんだけど何かあった?という通知もしてくれる。
LAN DISKを運用開始してから、このサービスで不具合に気づいたことがあり、一応機能していると思う。
不具合が起きているからってどうすりゃいいのかわからず、どうにもならず強制シャットダウンしたのだが・・・まあ、動いてないことに気づいてよかった。
とはいえ、運用開始から1ヶ月もしないうちによくわからない不具合が起きたというのに若干の不安を感じないでもない。
ちょっといじるにも何かと時間がかかる
先の不具合の確認や、バックアップの設定など、本機の各種設定や操作をしているときに、なんだかレスポンスが悪いのは気になる。
ちょっと何か設定してみようとしたら、ちょいちょい待ち時間が発生するので、あっという間に1時間くらい経っていたりするのだ。
まあ、NASとして最低限のスペックなんだろうから、設定画面の動きが遅いとかいうのはある程度許容するしかないのかもしれない。コストとの戦いだし。
細かいログも出ないから、今は何の処理中なのか、何を待っていればいいのかもよくわからなかったりする。もしかしたら設定ミスったかも?と思ってもう1回設定し直そうとしたら、処理中だから後にしてくれと言われることもあるし。
何かしらの設定をするときは、気長にできるときじゃないとブチ切れそうだ。
運用開始して、ファイル保管庫として使ったり、バックアップサーバとして使っている分にはそこまでパフォーマンスが気になることはないのだが・・・
細かいことがわからないストレス
NarSuSから不具合があったという事例だが、本体にアクセスすることもできなくなっていて、何が起こっているのかわからない状態だった。
電源ランプが緑点滅していることしかわからず、それは何かしらの処理中を意味するという。半日も処理中って何をやってるんだろう?
じゃあ、ちょっくら再起動しようとしても、シャットダウンを受け付けてくれない。電源ボタンを数秒押しているとピーッと鳴って、これがシャットダウンの指示らしいんだが、30分待っても何も起きないのだ。こうなったら電源ボタンを更に長押しして、強制的に電源を落とすしかないらしい。
ようやく再起動したところで、本機のシステムログを見ても、結局、何が起こっていたのか、何が原因だったのか、どういう状態だったのか、というのが全くわからない。
結局、困ったときは電源を引っこ抜いて強制終了し、また電源を入れるくらいしかできることがないみたい。それでファイルが消えても自己責任、と。
NASとしてパッケージングされているが故に、内部で何が起こっているのかサッパリわからなくなっているのが私にとってはストレスだ。対応も対処もしようがない。
これも割り切って付き合っていくしかなさそう。
おわりに
IO DATAのNASであるLAN DISK「HDL1-LE02」を導入してから1ヶ月が経っていたので、レビューしてみた。
NASとしてパッケージングされている製品だから、そんなに悩むことなく導入できて、導入してしまえばあとは使ってやるだけだ。
一方で、NASとしてパッケージングされている製品であるがゆえに、中で何が起こっているのかサッパリわからないところもある。困ったときは電源を抜き差ししての再起動をするしかない。多くの家電製品はそれでいいのかもしれないけど、ファイルサーバーがそれでいいのかと思うと不安を感じるところだ。
また、運用フェーズに入ってしまえば気にならないけど、各種設定をするためにWebの管理画面を操作していると、なんともレスポンスが悪く、結構な時間がかかったりする。不具合を確認したり、何かしらの機能を検証したりしようとすると、気がついたら1時間とか2時間とか経っていたりするのだ。なんとものんびりしたものだ。
とまあ、ちょっとアレコレやってみようとしたら気になるところは多々あるんだけど、運用開始してしまえばそこまでパフォーマンスが気になることはないし、NarSuSという監視サービスのおかげで異常があればわかるようになっている。
運用開始から1ヶ月以内によくわからない不具合が起こったので、信頼性については気になるところだが、この先、こういうのがよく起こるものなのか、たまたまだったのかは、しばらく使ってみての判断になりそう。
若干の癖を感じるが、本機の価格や、導入の手軽さを考えると、LAN DISKはそれなりに十分なNAS環境を構築できるものになっているんじゃないかと思う。
あんまり難しく考えずに使うのがよさそうだ。










