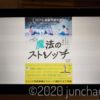「メモをとれば財産になる」はメモ術「ツェッテルカステン」の伝導書だった
「メモをとれば財産になる」を読んだ。
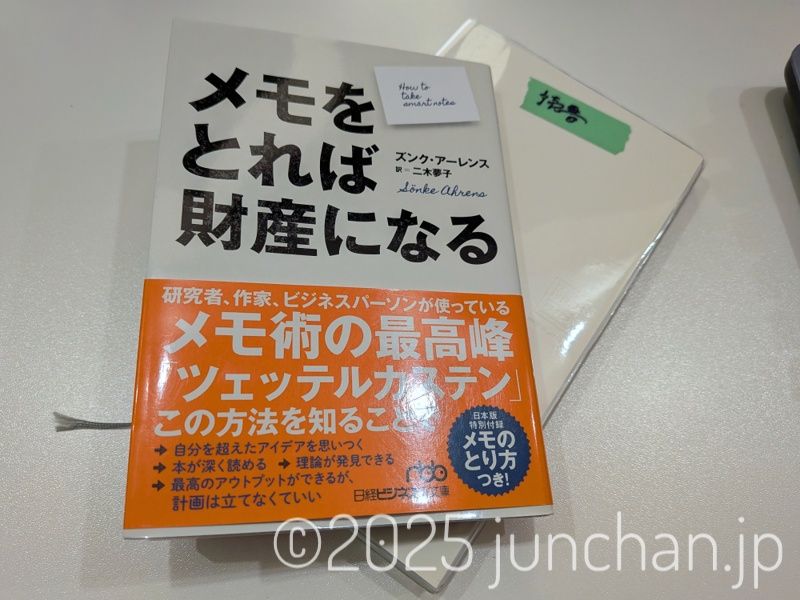
本書は「TAKE NOTES! メモであなただけのアウトプットが自然にできるようになる」の文庫版だそうだ。
Amazonの欲しいものリストの中にこの「TAKE NOTES!」が入っていたのを、買った後に気づいた。発売当初から気にはなっていたらしいが、ついぞ買わなかったらしい。そのころは放送大学のテキストばかり読んでいて、ビジネス書とかまでは手が回らなかったからなぁ。
「ツェッテルカステン」というメモ術
本書はメモ術の「ツェッテルカステン」を紹介した本で、このメモ術は私の中ではかなりインパクトがあった。かつてメモ術にはかなりアンテナを広げていたと自負しているのだが、ここ数年は学術活動に時間を割いていたこともあって、発見が遅れてしまったようだ。
なお、ツェッテルカステンが具体的にどういうメモ術かは、Googleで探せば色々出てくるし、さらに知りたければ本書を読んでもらうとして、ここでは詳細を述べるのはやめておこう。あくまで、私の所感を述べることに集中する。
本書を読んでいて思ったのは、私が普段、いろいろな形で取っているメモは、走り書きのメモ (メインメモに書いたら捨てるもの)か文献メモ (本を読んで学んだことを自分の言葉でまとめたもの)くらいだったんだな、ということだ。
そこからどう活用するかが私の中ではあまり明確ではなかったのだが、こうしたメモの先にあるものがツェッテルカステンという仕組みなんじゃないかと思った。私の場合は、メインのメモを起こすところまで行ってないんじゃないか、と。
これまでは、本を読んで学んだことを自分なりに活かしていたつもりだったんだけど、それはあくまで記憶を頼りにしていたわけで、そこを超えるにはツェッテルカステンのような仕組みが必要だと思えてきた。
本書は抽象度の高い言い回しで描かれているので (翻訳本あるある?)、私には一読しただけだと具体的にどんなメモを書き残すのがツェッテルカステン流なのかを掴みきれてないのだが、その辺はやりながら自分で掴むのがいいんだろうな、とも思う。
仕組みそのものはシンプルで、システム化するとしたらどうしたらいいかはおおよそイメージがついたし。
アイデアを蓄え、蓄えたアイデア間でリンクを形成し、そのネットワークが意味を持ってくるという発想は面白い。言われてみれば当たり前のような気もするんだけど、それをこんなふうに仕組み化した人がいたとは。
あと、私が普段取っているメモの中でも、あんまりこのツェッテルカステンに入れるものじゃないメモもいっぱいある気がするので、その辺の折り合いもどうつけていくのがいいか考えている。例えば、Linuxのとある機能の設定手順書みたいなものとか。プログラミングのコードの切れ端とか。この手のものは、再現性を確保するために詳細なメモが必要なものなんだけど、ツェッテルカステンはそういうメモを入れるものだとは思えなかった。
なにはともあれ、本書の中には、私がこれまで構築してきたメモシステムをアップグレードするヒントがいっぱいあった。
いいインスピレーションがもらえたので、このツェッテルカステンという方法を自分なりに実装していきたい。こういうのを考えているのが楽しい。