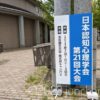放送大学で「福祉心理学」「障害者・障害児心理学」を履修した理由
放送大学の2022年度2学期に、「福祉心理学」を履修している。
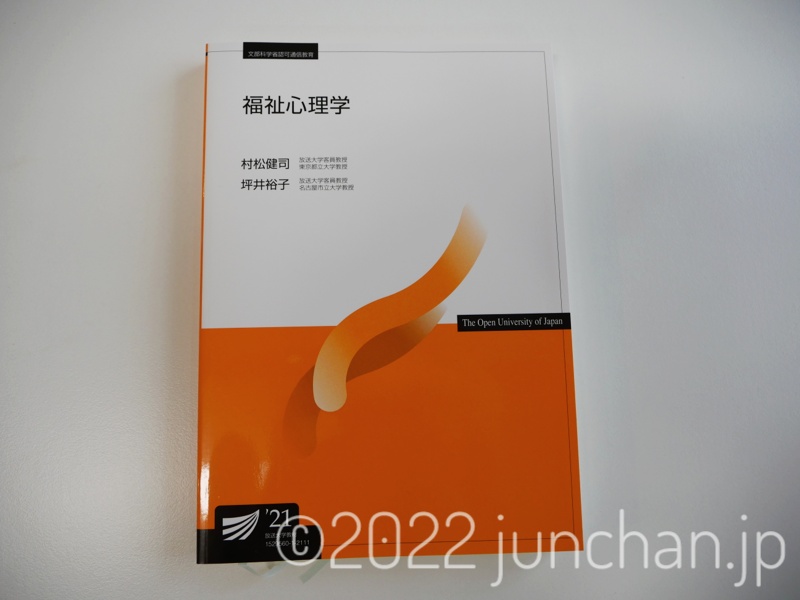
この科目を履修した理由は、主には認定心理士や公認心理師といった資格の取得要件になっているからだ。
それだけ、これからの時代、福祉の領域において心理士に求められることは知っておいて欲しい、ということなのだろう。
そのことは理解できるのだけれど、正直、個人的にはその内容にはそこまで興味がない。
福祉の領域で心理学が有効なことは理解できるし、その領域で心理士が必要とされることも理解できるけど、自分がそこに入っていって何かしたいか?というとあんまりそうは思わないからだ。
とはいえ、「大学で心理学を体系的に学ぶ」という当初の目的には合致しているから、この領域のことも満遍なく学んでおく、というスタンスである。
心理学が扱う領域は広大だから、すべてが楽しくて仕方がないということもなく、興味から外れてくる部分もあるだろう。
このことは、同じく2022年度2学期に履修している「障害者・障害児心理学」にも言える。
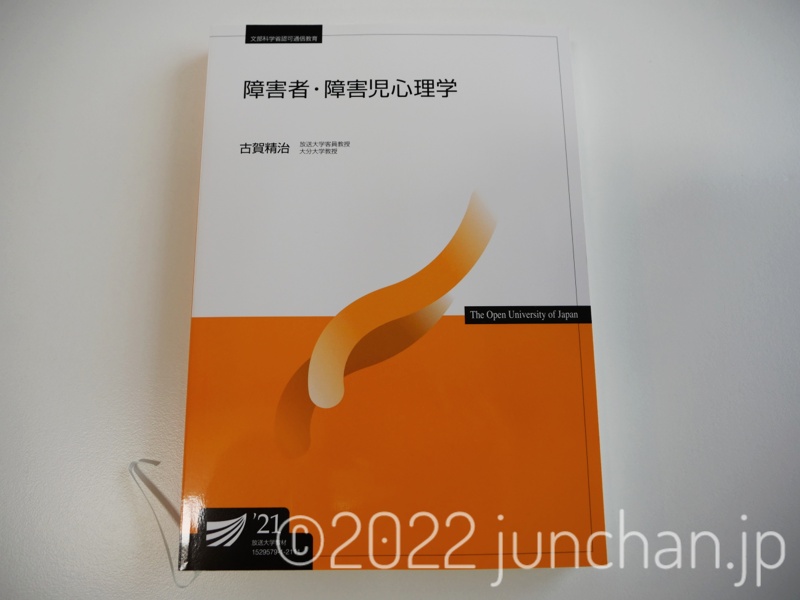
福祉の領域とかぶる部分もあるから、一緒に学んでおくと幅が広がるかな、と思い、福祉心理学と合わせて履修している。
なお、福祉心理学も障害者・障害児心理学はいずれもラジオ授業だ。このことも今学期に合わせて履修した理由だったりする。
テレビ授業はどうしてもパソコンの前で見ることになるから、テレビ授業ばかりにすると学習時間の確保が厳しい。その点、ラジオ授業であれば、洗濯や料理といった家事をしているときや、運転中にも学習できるため、学習時間を無理なく伸ばすことができる。つまりは、テレビ授業とラジオ授業を組合せて履修することで、大きく負担をかけることなく、学期中の学習時間を増やすことができるのだ。
両教科とも、それほど領域として興味がないにしても、別に消化試合にするつもりはなくて、やるからにはきちんと学ぶつもりだ。
実生活に照らし合わせつつ、有用な知見を身につけたい。