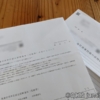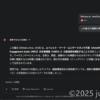映画「マネーボール」を鑑賞していると、学術的な心理学と重なる部分が見えた気がした
Amazonプライムビデオで映画「マネーボール」が見られるようになっていて、懐かしいなぁと思いながら見てしまった。

マネーボールは、私が会社員を辞めるか悩んでいたころに何度も見た映画である。
それから10数年後の今になって見ても、面白いドキュメンタリーだと思う。
当時の私にとっては、現状打破がテーマであり、それまでの考え方を脱してやっていくという覚悟を求めていたんだと思う。
劇中では、主演のブラピ演じるビリービーンが、アメリカのメジャーリーグ界の常識と真正面から戦う姿に痺れる。球界の大多数の人からダメだとか無理だとか、そんなのうまく行くはずがないと言われ、自分自信も迷いながらも、絶対これで行くんだ!という意思を貫いていく様が格好いい。
改めて鑑賞してみて思ったのが、それまで感覚的にやっていたことを、もっと客観的に判断できるものを使って評価し直してみよう、という姿勢がいいな、ということだ。
主人公は、メジャーリーグで優勝するために、野球の世界に統計学を持ち込んで、勝利できるチームを理論的に作る、という手法を採用した (セイバーメトリクス、というらしい)。このやり方が本当にいいかは別として、そうした新しい視点で野球界を評価し直そうとしたわけである。
従来は、選手の顔がいいとか、彼女がブサイクだとか、バットを振る音がすごいとか、投げ方が変だとか、かなり主観的なものさしで選手を評価していたそうだ。今でもそうなんだろう。まあ、全く理論的ではないというか、野球にそれ関係ある?と首をかしげるような内容もあったりする。
野球には夢があり、ロマンがある。そういう視点で見れば、こんな評価もあながち悪いとも言えないだろう。
そこに統計学なんてものを持ち込んだら、夢もロマンもへったくれもない。打つ選手は打つし、アウトになる選手はアウトになる。それは打率 (正確には出塁率)で決まる。投げ方が変だろうが、アウトを取れる投手は優秀だ。奪三振数、四死球数などで決まる。そういう評価になる。
ただ、科学的に野球を評価するなら筋は通っているような気がする。完全に評価しきれるかはわからないけど。
このことは、私が最近、大学の卒業研究で研究している心理学にも当てはまると思った。
心理学も、ものすごく乱暴に言えば、日常的には感覚でやっていることを、データを取って統計学で評価しようというものだ。
私たちは一人ひとりが自分なりに心理学を学んでいて (素朴心理学、という)、多くの場合はそれでなんとか生きていけるようにはなっている。
ただ、あくまで一人ひとりが自分なりに学んだものだから、ある人にとっては当たり前でも、ある人にとっては全くそんなことはなかったりする。これまたよくある話だろう。
そこに統計学を持ち込み、自然科学的な手法を使って、人の一般的な心理を明らかにしようという試みが学術的な心理学だ。
このところ心理学の研究をしている私には、素朴心理学と学術的な心理学のこういった違いが、マネーボールの世界に重なって見えた。
心理の世界に統計学なんて持ち込んだら、夢もロマンもへったくれもないだろう。ただまあ、そういう活動にも意味はあると思って、今日も研究に勤しんでいる。