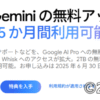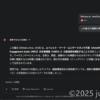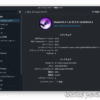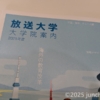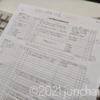NotebookLMを使って心理学論文を効率よく読み解く。論文をかき集め、その中で議論できるのが秀逸
今年度は放送大学で卒業研究を履修している。
研究を進めていくにあたり、論文を何本も読んでいるわけだが、これら論文をまとめてNotebookLMに投入し、議論していくと、なかなか効率よく情報が整理できるので気に入っている。
NotebookLMとは
NotebookLMは、Google社が提供している生成AI系サービスの1つだ。
私は大学生限定のキャンペーンにより、無料でGoogle AI Proを使っていて、NotebookLMもほぼ制限なく使うことができる。
これまでもGeminiを使って論文を読み解いたりしているが、NotebookLMはまたちょっと違った使い方ができるので重宝している。
GeminiとNotebookLMが違うのは、自分で情報源を指定することができることだろう。
Geminiでも論文を添付して、その中で議論ができるんだけど、何本もの論文を読み解くようにはなっていない。
その点、NotebookLMは、まずはソースとして複数の論文を読み込ませ、その中で議論ができるような作りになっている。おかげで、インターネット上にある有象無象の出どころのわからない情報を持ち込まないで済む。学術研究するなら、出どころのしっかりしたものを情報源としたいため、NotebookLMは相性がいいと思う。
もちろん、議論をよりよいものにするには、指定する情報源をよく選別することも大事なんだろうけど。
テーマごとにノートブックを作る
私の使い方としては、まずテーマごとにノートブックを作り、その中に、そのテーマに関する論文を10本くらいまとめている。
例えば、「コーチング」とか「モチベーション」といったテーマでノートブックを作って、それらをテーマにしている研究論文を追加していくわけだ。

テーマごとに議論する
そうして作ったノートブックの中で、そのテーマに関する議論をする。
例えば、「コーチングはどういうものと定義されていますか?」といった質問をしてやると、ノートブックにある論文の中から答えを示してくれる。
この際に、どの論文のどのあたりからそのことが言える、という引用まで示してくれる。これはものすごく便利。
論文執筆する際にも参考にできそうだ。こういう文脈でこの論文をこうやって引用することもできるのか、とか。
英語論文でも日本語論文でも構わずまとめてくれるから、言語を問わず使えるのもいい。
テーマによっては国内の論文はそれほどなくて、海外の英語論文の方が多いものも少なくないので、非常に助かる。
こうして、いくつもの論文を情報源として、そのテーマにはどんな話題があるか、どんな実験をしているのか、結果はどう解釈しているのか、といったことをまとめられるのがすごい。
普通なら自分で論文を5本、10本と読んでまとめるわけだが、NotebookLMに論文をまとめることで一気に確認できるのはすごいことだ。何本も読んでいるうちに、前のものはどんどん忘れていくもんな・・・
音声解説を聞く
ノートブックを作ったら、「音声解説」を使うのもいい。
そのノートブックにアップした論文のサマリを、2人の掛け合いトークショーみたいな感じで音声により解説してくれるのだ。
この機能をはじめて使ったときはびっくりした。およそ10分に満たない時間で、よく要点をまとめてくれている感じがする。
この音声解説を聞くと、その分野に関する一般的な情報を得られた感じすらする。
ざっくり概要を掴みたいのであれば、このくらいで十分かも?と思えてしまう。
もちろん、本当に音声解説の言ってることが正しいかは、自分がアップした論文に当たるべきなんだが、それにしたって時間を要するものだから、ある程度は生成AIを信じ、そのくらいで調査を終えてもよいものだってあるだろう。
おわりに
卒業研究を進めるにあたって、NotebookLMを活用している。
NotebookLMの便利なところは、複数の論文をまとめて議論できることだ。私が選んでアップロードした論文集を情報源として、その中で議論ができる。これがいい。
特定のテーマごとにノートブックを作れば、さらに突っ込んだ調査もできるというもの。
学術研究において、NotebookLMはすごく使えるやつだと思う。
もはや私の卒業研究には、なくてはならないサービスである。