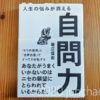「書ける人だけが手にするもの」どうやって文章を書くか?のヒントが見つかる本
齋藤孝さんの「書ける人だけが手にするもの」を読んだ。
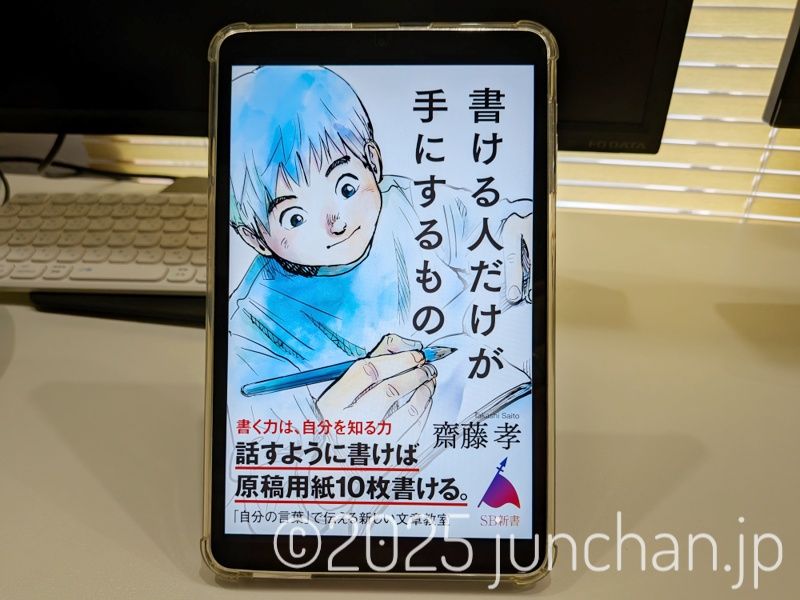
最近は本を読むことや書くことに関して色々と思うことがあり、本書が目に留まった。
書ける人だけが手にするものって、なんだろう?と。
書ける人だけが手にするもの
私はこうしてブログを書いているし、メルマガも書いているし、その他にも日々大量に何かしらを書き綴っている。
昨今はリモートワーク時代だからこそ、ますます書くことが増えているし、書くことの重要性が増していると考えていて、書くことに対して色々と思うことがある。
そんな背景もあって、文章術のようなジャンルには結構、意識が向いている。
本書の中には、文章を書くためのヒントが色々とあって、すぐに実践できそうなものから、ちょっとじっくり考えたいと思うものまであった。
本書によると、文章を書くには何かしらの「フック」が必要で、その「フック」が定まれば結構文章は書けるものだったという。
例えば、エッセイなんかは、何かしら自分が体験したエピソードをフックに、自分の考えを書き綴ったりすることで文章ができ上がってくる。つまり、「エピソード + 自分の考え」が、一つの文章の型になるのだ。
このブログなんかはまさにこのエッセイの型だろう。どこかに行ったとか、何かを食べたとか、この本を読んだとか、そういうフックを基にして、私なりに思ったことや考えたことを書き綴っている。この記事なんて、この本を読んだことをフックにして、思い当たったことを書いているわけだ。
そう考えると、このエッセイの型はよくやっていると思う。書き物だけじゃなく、日常的に会話する中でも、このエッセイの型のエピソードトークはよくやるものだ。社員研修でもやるし、コーチングでもやる。エンジニアが集まる朝会でもやる。
このようなエッセイの型はかなり汎用性が高いと思うし、文章の書き方としてすぐにでも実践できることだろう。
本書によると、こうした書き始めのフック、言うなればネタのようなものは、自分の体験以外にも色々あって、概念とか、文献の引用とか、疑問点などもフックになるという。
引用で言えば、ここで本書の中から一文でも紹介して、それについて私はこう考えた、こう捉えた、なんて書けば、それは一つの文章に仕上がるわけだ。そう考えると、本というのはフックの宝庫である。
また、ふと疑問を感じたことに、自問自答して突き詰めていけば、それは論文にだってなるだろう。
結局のところ、いろいろなフックを持っておくことが、文章を書くにあたって起点となるのだから、意識して過ごすことが大事になってくる。私なんて、このブログを1日1本は公開すると決めているので、毎日フックを探している。
こういう姿勢でいることで、自分と世界のつながりが強くなって、日々を漫然と過ごすことがなくなる。それは目の前の事象や物事をよく考えることに繋がるんだろう。本書の中でも、こういう姿勢でいることが「考える人になる」と表現していた。これも書くことが与えてくれるメリットだ。
あと、私は文章を書くことによって、考えをまとめるということをよくやっている。書くことを通じて、思考を深めることができるのだ。これが私の日々の活動を支えているし、もっというと食い扶持にもつながっている。
こうしたことも、書ける人が手にしているものと言えるんだろうな。
そんな感じで、本書の中には文章を書くためのヒントがたくさんあって、なるほどそうかと思うことが多々あった。普段あまり使っていないフックとかある気がしたし、そういうものに対する感度を高めていきたいものだと思った。